認知症の資格・研修体系を網羅・解説~義務化からキャリアアップ、給与・加算への影響まで

認知症ケアの現場では、日々の小さな工夫や確かな知識が、ご本人やご家族の安心につながります。いま、介護職員には「専門性のある認知症ケア」が強く求められています。
「認知症ケアの研修ってどこまで受ければいいの?」「研修を受けると給与や評価にどうつながるの?」
――介護職員や事業所の多くが抱える疑問ではないでしょうか。2024年度から始まった認知症介護基礎研修の義務化を皮切りに、研修・資格体系は“認知症ケアは現場での必須スキル”として位置づけられつつあります。
本コラムでは、認知症に関する研修体系の全貌と義務化の背景から、キャリアアップ・給与・加算への影響までを徹底解説。「認知症ケアの専門家」への道を切り開くために、いま何を学び、どう行動すべきかを明らかにします。
- 1.なぜ今、認知症に関する研修が必要なのか?
- 2.義務化された「認知症介護基礎研修」とは ~介護現場で求められる知識と実践力
- 3.認知症介護実践者等養成事業として ~「公的研修」の構造とロードマップ
- 4.認知症専門家としての「民間資格」
- 5.資格取得メリットと具体的な活用法
- 6.まとめ 今後の動向
1.なぜ今、認知症に関する研修が必要なのか?
認知症介護の専門性、不可欠な時代へ
日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでいます。内閣府の調査によれば、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症を発症すると推計されており、認知症は「特別な病気」ではなく、誰もが関わる可能性のある身近な課題となりました。
その一方で、認知症の症状や行動は個人差が大きく、記憶障害や見当識障害だけでなく、不安・幻覚・徘徊・暴言など、多様な行動心理症状(BPSD)が現れることがあります。こうした症状は、本人の尊厳を損なうだけでなく、介護者や家族の大きな負担となる場合も少なくありません。
このような背景から、介護現場で求められるのは「単なる日常生活の支援」ではなく、認知症に関する科学的理解に基づき、一人ひとりの状態に合わせた適切なケアを実践できる専門性です。介護職員が十分な知識と技術を持つことで、利用者の安心と尊厳を守り、家族の負担を軽減し、さらには職員自身のストレスを減らすことにもつながります。
つまり、認知症介護は「誰にでもできる仕事」から「高度な専門職」へと進化しており、その基盤としての研修が不可欠な時代になっているのです。
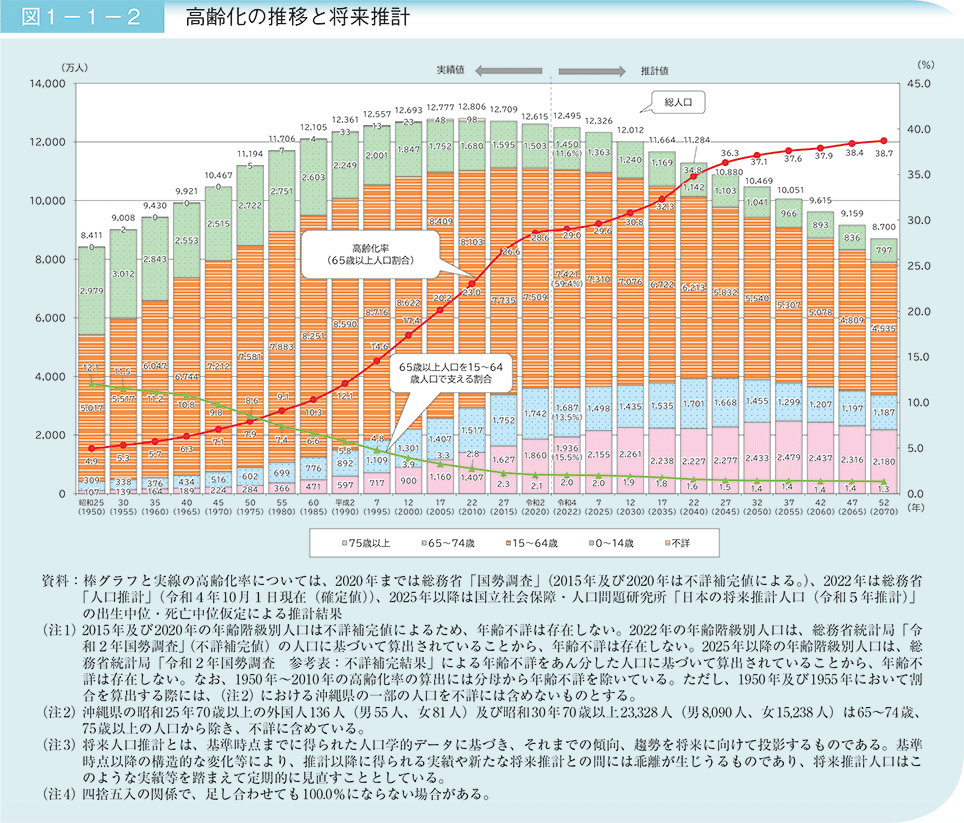
日本の認知症施策の変遷と法的基盤
認知症施策の整備は、2000年に介護保険制度が始まった頃から本格化しました。当初は制度の中で「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」が創設されるなど、限定的な対応にとどまっていましたが、その後、認知症の増加に伴い国の政策は大きく変化していきます。
2004年には「痴呆」から「認知症」へと呼称が変更され、社会的理解を深めるための第一歩が踏み出されました。さらに、2012年には「オレンジプラン」、2015年には「新オレンジプラン」が策定され、医療・介護・地域が連携して認知症高齢者を支える包括的な体制づくりが進められました。
そして、2023年には「認知症基本法」が成立。これにより、認知症施策は努力目標ではなく、法律に基づく国家的課題として位置づけられました。この法律は、認知症の人の尊厳を尊重し、社会全体で支える仕組みをつくることを目的としており、研修や教育の普及はその柱の一つです。
特に重要なのは、2024年度から「認知症介護基礎研修」が全国で義務化されたことです。これは、認知症ケアに直接携わる介護職員は、必ず一定の研修を受けなければならないと定めたものであり、現場の標準的な知識と技術を底上げするための大きな一歩といえます。
このように、日本の認知症施策は、制度創設から20年余りの間に「限定的支援」から「法的に裏づけられた全国的な取り組み」へと進化してきました。その中心に位置づけられているのが、介護職員の教育研修なのです。
公的研修と民間資格
認知症介護に関する研修体系は、公的に定められた研修と、民間団体が認定する資格の二本柱で構成されています。
まず、公的研修の代表が「認知症介護基礎研修」です。これは認知症ケアに携わるすべての介護職員が修了することを求められており、認知症の理解、基本的なコミュニケーション技術、BPSD※1への初期対応などを学びます。続いて「実践者研修」では、より応用的な対応力を養い、「実践リーダー研修」や「指導者養成研修」では、チームをまとめ、職場全体のケアの質を引き上げる能力を身につけます。これらの研修は、介護報酬の加算要件とも結びついており、事業所経営にも直結する重要な制度です。
一方で、民間資格も大きな役割を果たしています。たとえば「認知症ケア専門士」や「認知症ライフパートナー」などは、公的制度には含まれませんが、より深い知識を得たり、キャリア形成や自己研鑽の証明として活用されたりしています。これらの資格を持つことで、現場での信頼性が高まり、転職や昇進に有利になることもあります。
つまり、公的研修は「必須の基礎体力」をつけるための制度であり、民間資格は「さらなる専門性」を磨くための選択肢といえます。両者をうまく組み合わせることで、介護職員は制度に対応するだけでなく、自らのキャリアを積極的に築いていくことが可能となるのです。
※1(「認知症の行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)」の略で、認知症の方に見られる不安、抑うつ、幻覚、妄想、焦燥、徘徊などの行動や心理的な症状全般)
2.義務化された「認知症介護基礎研修」とは
~介護現場で求められる知識と実践力
認知症研修の目的と法的背景
認知症の人の増加に伴い、介護現場に携わるすべての職員が認知症に関する正しい理解と適切な対応を身につけることは喫緊の課題となりました。
その背景には、2021年度の介護保険法改正があり、介護に従事するすべての無資格職員に対して「認知症介護基礎研修」の受講を義務づける制度が整備されました。法律上の根拠は介護保険法施行規則であり、事業所は職員に受講機会を与える義務を負います。単なる努力目標ではなく、事業運営の必須要件と位置づけられた点が大きな特徴です。研修の目的は「認知症の人を理解し、尊厳を守るケアを実践できる人材の底上げ」にあります。
介護系資格の無資格者と有資格者の違いと認知症介護基礎研修の免除条件
「認知症介護基礎研修」の対象は主に介護施設や在宅サービス事業所で働く無資格の介護職員です。介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者など、既に一定の介護資格を持つ人は、研修内容と重複するため受講が免除されます。
一方で、資格を持たずに現場で働く職員や、資格取得を目指す前段階の人材にとっては必須です。これにより「知識ゼロで現場に立つ」状況を避け、最低限の理解と倫理観を備えたうえでケアにあたる仕組みが整えられました。また、看護師や社会福祉士といった他分野の国家資格者も、一部自治体では免除対象とされています。免除の可否は都道府県ごとに細則が異なるため、所属事業所を通じて確認することが重要です。
修了のメリットと事業所に課される義務
受講を修了した職員にとってのメリットは大きく二つあります。第一に、認知症ケアの基本を体系的に学ぶことで、日々のケアの自信につながり、仕事のやりがいを感じやすくなる点です。第二に、修了証は将来的に資格取得やキャリア形成の基盤として評価される可能性が高い点です。職場内での信頼性向上にも寄与します。
一方、事業所には「雇用している無資格職員に対し、1年以内に研修を受講させる義務」があります。もし職員を受講させない場合、行政指導の対象となり、最悪の場合は指定取消のリスクさえあります。事業所にとっても人材育成と法令遵守の両面で欠かせない制度であり、研修受講の管理は運営上の必須業務となっています。
研修カリキュラムと学習内容
研修カリキュラムは、全国で共通の大枠が定められており、おおむね6~8時間程度の学習で構成されています。主な学習内容は以下の通りです。
| 項目 | 学習内容の概要 | ポイント |
| 1. 認知症の基礎知識 | 種類(アルツハイマー型、レビー小体型など)、症状の進行、医学的背景 | 認知症を「病気」として正しく理解する |
| 2. 認知症の人への理解 | 本人の気持ちや行動の背景、尊厳を守る視点 | 行動の裏にある不安や混乱を理解する姿勢 |
| 3. ケアの基本姿勢 | 安心感を与える接し方、日常生活支援の工夫 | 「できることを活かす」支援を重視 |
| 4. コミュニケーション方法 | 言葉がけ、表情や身振りなど非言語的支援、家族との連携 | 双方向のやり取りを大切にする |
| 5. 介護現場での実践例 | BPSD(徘徊、幻覚、暴言など)への対応、事故防止 | ケースを通じた実践的理解 |
| 6. 権利擁護と倫理 | 虐待防止、意思決定支援、法的枠組み | 利用者の人権と尊厳を守る基盤となる視点 |
カリキュラムは講義形式だけでなく、ケーススタディや映像教材を交え、理解を深める内容となっています。知識の習得に加えて、介護職員としての姿勢や価値観を養うことが狙いです。
受講方法、費用、難易度
受講方法は、各都道府県や指定機関が実施する集合研修とオンライン研修の2種類があります。コロナ禍以降はeラーニング方式が拡充し、働きながらでも受講しやすい環境が整っています。
費用については、原則として事業所負担とされることが多く、1人あたり数千円程度(3,000~5,000円前後)が相場です。国や自治体が補助を行うケースもあり、実質的に無料で受けられる場合も少なくありません。
難易度は決して高いものではなく、基本的な理解を確認するレベルです。修了試験は選択式やレポート形式で行われることが多く、通常は受講すれば修了できる内容です。ただし「単なる義務」ではなく、現場での実践に直結する内容であるため、受講者の姿勢によって得られる成果は大きく変わります。
「認知症介護基礎研修」の義務化は、単なる制度の変更にとどまらず、日本の介護現場全体の底上げを意図した大きな改革です。無資格で現場に入る人材も含め、誰もが一定の知識と理解を持ってケアにあたることが、利用者本人と家族の安心につながります。事業所にとっては人材育成とコンプライアンスを両立する手段であり、職員にとってはキャリアの第一歩として位置づけられます。
認知症ケアは「知識」と「理解」の両輪で成り立ちます。本研修を出発点に、すべての介護職員が学び続け、尊厳ある生活を支える力を伸ばしていくことが求められています。
3.認知症介護実践者等養成事業として ~「公的研修」の構造とロードマップ
高齢化の進行、認知症の人の増加、こうした状況に対応するため、国は介護職員の認知症ケアに関する専門性向上を目的として「認知症介護実践者等養成事業」を位置づけ、段階的な研修体系を整備してきました。本事業の最大の特徴は、基礎から指導者レベルまでを一貫したロードマップとして示している点にあります。
最初の入り口となるのが「認知症介護基礎研修」です。これはすべての介護職員が認知症ケアに必要な基礎知識と理解を習得するための研修で、2021年度から受講が義務化されました。認知症の症状や行動・心理症状(BPSD)への対応、本人主体のケアのあり方など、日常業務に直結する認知症に対する基礎知識を身につけることを目的としています。
次のステップが「認知症介護実践者研修」です。ここでは基礎で学んだ知識を実際の現場に応用し、より具体的なケアの実践方法を学びます。ケーススタディや演習を通じて、個別ケアの工夫や家族支援、多職種との連携のあり方を深め、現場で「実践力」を発揮できる人材を育てます。
さらに、その上位に位置づけられているのが「認知症介護実践リーダー研修」です。実践者研修を修了し、現場で中心的な役割を担う人材が対象となります。この研修では、チームマネジメントや後輩職員への指導・助言、課題解決のためのリーダーシップなどを学びます。単なる介護技術の習得にとどまらず、組織としてのケアの質を高める推進役としての役割が期待されます。
最上位に位置づけられるのが「認知症介護指導者養成研修」です。ここでは研修の企画・運営や教育技法、地域包括ケアとの関連までを学び、事業所や地域全体の認知症ケアを底上げできる指導的人材を育成します。修了者は自治体や地域の研修講師、あるいは政策形成の一端を担うなど、広域的な役割を果たすことが期待されます。
| 研修名 | 目的・役割 | 主な研修内容 | 研修期間・形式 |
| 認知症介護実践者研修 | 認知症介護基礎研修を修了した職員が、現場でより実践的・専門的な対応ができるようになることを目的とする。ケアの質を高め、利用者に応じた柔軟な支援を担う。 | ・認知症の症状理解の深化・BPSD(行動・心理症状)への具体的対応・ケーススタディを通じたケアの工夫・家族支援やチームケアの実践 | おおむね 数日〜1週間程度(講義・演習中心)。都道府県により日数・時間数は異なる。 |
| 認知症介護実践リーダー研修 | 実践者研修を修了し、チームの中核を担う職員が対象。現場でリーダーシップを発揮し、他職員を指導・助言する役割を育成する。 | ・ケアチームの指導・助言方法・認知症ケアのマネジメント・多職種連携の推進・課題解決に向けたリーダーシップ実践 | 5〜10日程度(講義+グループワーク+実習)。自治体によって構成が異なる。 |
| 認知症介護指導者養成研修 | 地域や事業所全体で認知症ケアの水準を引き上げる役割を担う「指導者」を養成。研修企画や人材育成、政策レベルでの関与も期待される。 | ・研修企画・運営方法・教育技法、指導者としてのスキル・地域包括ケアと認知症施策の理解・実地研修・指導実習 | 数週間〜数か月間、延べ数十〜数百時間。講義・演習・実習を含む。高度な内容。 |
このように、基礎研修から始まり、実践者、リーダー、指導者へと発展する体系は、個々の職員のキャリアパスとしても機能しています。介護現場で働きながら段階的に学びを深めることで、専門性が高まり、やりがいと成長を実感できるのです。また、これらの研修修了は介護報酬加算や処遇改善にも直結する場合があり、給与やキャリアアップの観点からも大きな意味を持っています。
認知症介護は、単に介助の技術ではなく、「その人らしさ」を支える包括的な支援です。そのためには、体系的な学びを通じて専門性を積み重ねることが不可欠です。公的研修のロードマップは、その道筋を明確に示すものであり、介護職員一人ひとりが未来のケアの担い手として成長していくための大切な指針といえるでしょう。
4.認知症専門家としての「民間資格」
認知症介護に関わる学びの体系には、国が整備した公的研修のロードマップが存在しますが、それと並行して数多くの「民間資格」も広がっています。民間資格は法的な義務や公的研修のような全国統一の枠組みこそありませんが、現場のニーズや専門分野に特化した学びを提供し、介護職員や看護職員がスキルアップやキャリア形成を考えるうえで大きな選択肢となっています。
代表的な資格としては、「認知症ケア専門士」が挙げられます。これは全国規模の学会が認定するもので、筆記試験や面接試験を通じて、認知症に関する医学的知識、介護技術、倫理観などを体系的に問われます。受験には一定の実務経験が必要であり、合格すれば認知症ケアの専門家として全国的に通用する称号を得ることができます。学術的裏付けと実践力の両立を重視しており、資格取得者は施設内でのリーダー役や研修講師、地域の啓発活動に携わることも少なくありません。
また、「認知症ライフパートナー検定」や「認知症ケア指導管理士」といった資格も注目されています。これらは幅広い職種を対象にしており、介護職員だけでなく、看護師、医療ソーシャルワーカー、地域包括支援センターの職員なども学びの対象となります。認知症の症状理解やBPSDへの対応方法、本人や家族への心理的支援、権利擁護の視点など、実務で役立つ知識を体系的に学べるのが特徴です。検定形式の資格は段階的に受験できるものもあり、基礎から応用へと学びを積み重ねられるため、自己研鑽のモチベーション維持にもつながります。
| 資格名 | 運営団体 | 受講・受験要綱 | 費用目安 | 取得期間目安 | 主な目的・役割 |
| 認知症ケア専門士 | 一般社団法人 日本認知症ケア学会 | 受験資格:実務経験(介護・医療・福祉分野で原則5年以上)など試験:筆記試験+口述試験 | 受験料 約20,000円、認定料 約10,000円 | 合格後、認定登録までに約1年 | 認知症ケアの総合的専門家。科学的知識と実践力を兼ね備え、現場でのリーダー的役割を担う |
| 認知症ケア上級専門士 | 日本認知症ケア学会 | 認知症ケア専門士を取得し、一定の実務・研究実績を有する者が対象試験:論文審査・口頭試問 | 受験料 約30,000円 | 審査・合格後に認定 | 高度な専門性と教育力を持ち、研修講師や研究活動を通じて認知症ケアを発展させる |
| 認知症ケア指導管理士 | 一般財団法人 職業技能振興会 | 学歴・経験要件なし(誰でも受験可能)試験:年数回実施、マークシート形式 | 受験料 約15,000円 | 受験〜合格まで数か月 | 認知症ケアの知識を持ち、現場職員の指導やケア管理を行う人材育成 |
| 認知症介助士 | 公益財団法人 日本ケアフィット共育機構 | 学歴・経験要件なし通信講座+試験方式(在宅受験可) | 受講料・受験料 約20,000円 | 約2〜3か月 | 認知症の基礎理解を身につけ、一般市民から介護職員まで幅広く「認知症にやさしい社会づくり」に貢献 |
| 認知症ライフパートナー検定 | 一般社団法人 日本認知症コミュニケーション協議会 | 学歴・経験要件なし試験:3級(基礎)〜1級(上級)まで段階制 | 受験料 3級 約5,000円、2級 約7,000円、1級 約10,000円 | 学習+受験で数週間〜数か月 | 認知症の人とのコミュニケーションに重点を置き、本人や家族を支えるスキルを評価 |
民間資格の魅力は、その柔軟性と多様性にあります。公的研修が「誰もが受けるべき共通基盤の学び」であるのに対し、民間資格は個人の興味やキャリアビジョンに応じて選択できるのが強みです。たとえば、現場リーダーとして組織をまとめたい人はマネジメント色の強い資格を、認知症ケアの心理的支援を深めたい人はカウンセリング寄りの資格を選ぶ、といった具合です。
一方で注意すべき点もあります。民間資格は発行団体ごとに基準や内容が異なるため、取得すれば必ずしも給与や昇進に直結するわけではありません。資格を選ぶ際には、発行団体の信頼性、学習内容の実用性、現場での評価を十分に確認することが重要です。また、資格取得が目的化してしまうのではなく、日々のケアの質向上にどう生かすかを意識することが求められます。
公的研修と民間資格は、対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。公的研修で基礎と標準を身につけ、民間資格で特化した領域を深める――その組み合わせが、認知症専門家としての成長に大きな力を発揮します。これからの介護現場では、両者をバランスよく活用することが、職員一人ひとりのキャリア形成と、認知症の人や家族にとって安心できるケアの実現につながっていくでしょう。
5.資格取得メリットと具体的な活用法
介護現場では、認知症ケアの専門性が求められる中、民間資格や公的研修を活用してスキルを高める職員が増えています。資格取得は単なる自己研鑽ではなく、給与やキャリア、組織運営、介護の質向上にも直結します。本稿では、個人、事業所、費用面の三つの視点から、資格取得のメリットと活用法を整理します。
個人へのメリット: 給与・キャリアアップの道筋
介護職員が認知症関連の資格を取得する最大のメリットの一つは、キャリア形成と給与面でのプラスです。例えば、「認知症ケア専門士」や「認知症ケア指導管理士」といった資格は、専門性を証明する公的・民間の認定資格として評価されるケースが多く、処遇改善や昇給の判断材料になることがあります。
実際、資格取得者はリーダーや研修担当者として活躍できる可能性が広がります。基礎研修や実践者研修だけでなく、上級資格を持つ職員は、チーム内で指導役として業務をまとめたり、新人教育に携わったりすることが可能です。これにより、組織内での責任あるポジションに就く機会が増え、結果として給与や手当の向上につながるケースも少なくありません。
また、資格取得は職員自身の専門性の証明として履歴書や職務経歴書に明記できるため、転職やキャリアチェンジの際にも有利に働きます。認知症ケアは高齢化社会でニーズが高まる分野であり、資格を持つことで「専門家」としての市場価値を高めることができるのです。
事業所・組織へのメリット: ~「認知症専門ケア加算」
資格取得のメリットは個人だけでなく、事業所や組織にとっても大きな意味があります。まず、認知症関連資格を持つ職員が増えることで、介護の質が向上します。専門知識をもとにした個別ケアやBPSD対応が可能となり、利用者や家族の満足度が高まるだけでなく、事故やトラブルの予防にもつながります。
さらに、資格取得は事業所の収益面でも有利に働きます。介護報酬の加算の一つである「認知症専門ケア加算」は、研修を修了した職員が一定数以上在籍している場合に適用されます。具体的には、認知症ケア専門士や実践者研修修了者などの資格保有者がチームに加わることで、加算対象となり、事業所の収益向上につながります。
また、資格取得を通じて職員が専門的知識を共有することで、職場全体のスキルアップも期待できます。新人指導やチーム内の情報共有、ケアプラン作成時の助言など、資格取得者が中心となることで、組織全体の介護の質が底上げされます。これは、長期的に見れば施設の評判向上や利用者増加にも結びつく重要な効果です。
認知症専門ケア加算の算定要件と報酬一覧
| 加算区分 | 算定要件 | 単位数(1日あたり) | 備考 |
| Ⅰ | ・日常生活自立度Ⅱ以上の認知症高齢者が利用者の50%以上・認知症介護実践リーダー研修等修了者の配置(人数は対象者数に応じて)・専門的な認知症ケアの実施・認知症ケアに関する会議の定期開催 | 3単位 | 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護などで算定可能。 |
| Ⅱ | ・加算Ⅰの要件を満たす・日常生活自立度Ⅲ以上の認知症高齢者が利用者の20%以上・認知症介護指導者研修修了者の配置・介護職員・看護職員ごとの研修計画の作成・実施 | 4単位 | 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護などで算定可能。 |
認知症ケア加算に関する詳細記事はこちら
費用負担と事業所支援策
資格取得には、受講料・受験料・教材費などの費用がかかります。たとえば、認知症ケア専門士であれば総額2〜3万円程度、上級資格ではさらに高額になる場合があります。職員個人が全額負担すると経済的負担が大きく、取得意欲が低下することも考えられます。
そこで、事業所としては職員の資格取得を支援する仕組みを整えることが有効です。具体例としては以下のような支援策があります。
- 費用補助制度:受講料や受験料を一部または全額事業所が負担する。
- 勤務時間内の学習支援:研修受講日を勤務時間として扱うことで、個人負担を軽減する。
- 資格取得手当:資格取得者に毎月一定の手当を支給する。
- キャリアパスの明示:資格取得によって昇格や役職任命の機会があることを明示する。
こうした支援策により、職員は経済的・時間的負担を軽減しながら資格取得にチャレンジでき、結果として個人のスキルアップと組織の介護力向上を両立させることが可能になります。
認知症関連資格の取得は、個人にとってはキャリア形成と給与アップのチャンス、事業所にとっては介護の質向上と収益向上の手段として、大きなメリットがあります。資格取得にかかる費用や時間を適切に支援することで、職員の学習意欲を高め、組織全体の専門性を底上げすることができます。
介護現場において「認知症専門家」として成長することは、利用者や家族に安心を提供するだけでなく、職員自身のやりがいやキャリアの充実にもつながるのです。個人と事業所の双方がメリットを享受できるよう、資格取得を戦略的に活用していくことが、これからの介護現場における重要な取り組みといえるでしょう。
6.まとめ 今後の動向
「なぜ今、認知症に関する研修が必要なのか?」という問いに対する答えは明確です。社会全体で認知症の人を支えるために、介護現場の専門性は欠かせません。そしてその専門性は、制度と法律に裏づけられた公的研修によって最低限の水準が保証され、さらに民間資格や自主的な学びによって磨かれていきます。
これからの介護職員に求められるのは、単なる義務として研修を受けるのではなく、「認知症ケアの専門家」として成長するための機会として研修を活用する姿勢です。学び続けることが、利用者の生活の質を高め、家族を支え、そして自らのキャリアとやりがいを豊かにしていく道につながっていくでしょう。
認知症介護の資格・研修は、専門性を高め、キャリアアップにつながる“学びのロードマップ”です。基礎研修から実践者、リーダー、指導者へ段階的に学ぶことで、現場での対応力や判断力が確実に向上します。資格取得は給与や加算制度にも反映され、キャリアの明確なステップにも。義務として受けるだけでなく、自らの成長と利用者の安心のために活用することで、あなたも「認知症ケアの専門家」として活躍できます。
今後、認知症介護の資格・研修体系はさらに整備・高度化が進むと予想されます。義務化の対象範囲の拡大や研修内容の充実、実践的スキルの評価方法の見直しが進むことで、より現場に即した専門性が求められるようになるでしょう。また、資格取得と介護報酬加算の連動も強化され、キャリア形成や待遇改善との結びつきが一層明確化されます。介護職員にとっては、継続的な学びと自己研鑽が、専門家として成長する最大のチャンスとなる時代です。
日々の研修にお悩みならツクイスタッフの研修サービスがおすすめです。業務に追われる職員に無理なく学べる研修を「動画研修「Ecarelabo」・集合研修」のスタイルで提供しています。話題のBCPや法定研修、介護技術の向上に関する研修も豊富です。進捗管理も容易ですので管理者の手間も省けます。
動画研修は無料トライアルもございますので、お問い合わせしてみてください。
法定研修の詳細記事はこちら
参考文献
- 「認知症介護基礎研修標準テキスト」 認知症介護研究研修センター(ワールドプランニング)
- 「認知症介護実践研修テキスト 実践者編」
- 認知症介護実践研修テキスト編集委員会(中央法規出版)
- 「認知症介護実践研修テキスト 実践リーダー編」
- 認知症介護実践研修テキスト編集委員会(中央法規出版)
- 「新訂・認知症介護実践リーダー研修 標準テキスト」
- 認知症介護実践研修テキスト編集委員会(ワールドプランニング)
- 「介護職キャリアアップ~実践手法と情緒的思考~」 工藤健一郎(デザインエッグ社)
- 「福祉・介護の仕事&資格がわかる本」 資格試験研究会(実務教育出版)
- 「福祉・介護の資格と仕事 やりたい仕事がわかる本」 梅方久仁子(技術評論社)
- 「介護職員初任者研修テキスト第2版」 太田貞司・上原千寿子・白井孝子(中央法規)

 資料ダウンロード
資料ダウンロード お問い合わせ
お問い合わせ ログイン
ログイン






